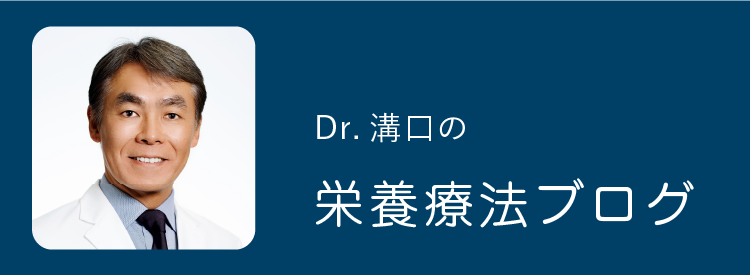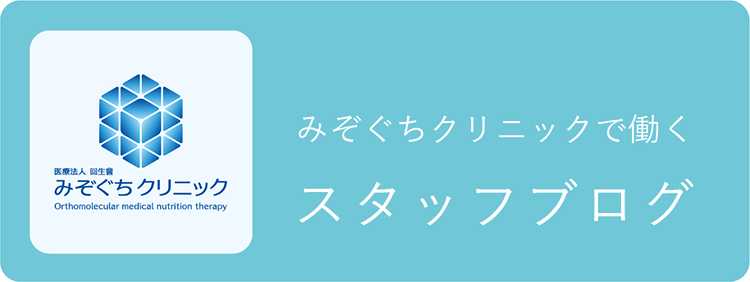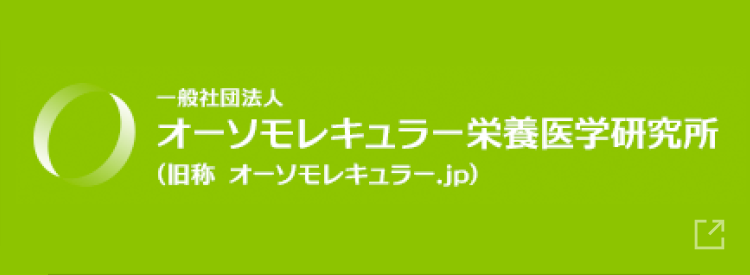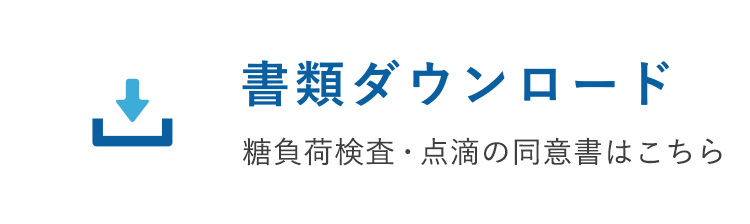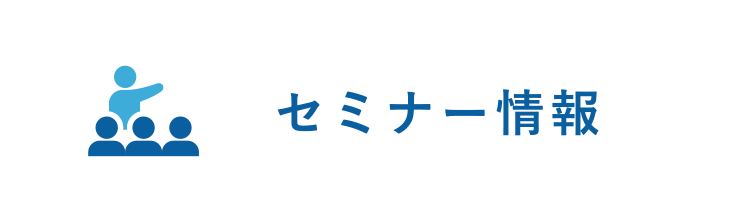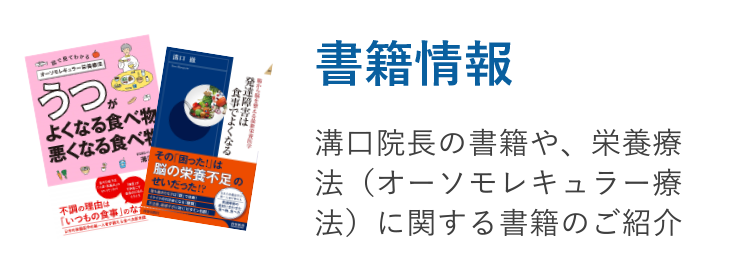オーソモレキュラー栄養療法 (旧 新宿溝口クリニック)
 アクセス
アクセス
- 診療時間
- 平日 9:30-13:00、14:30-18:00
- 休診日
- 第1・3・5木曜、日祝日、各季節休暇
お悩み・疾患別治療 SYMPTOMS
- 月経に伴う不調(PMS)とオーソモレキュラー栄養療法
- オーソモレキュラー栄養療法とPMS
- 月経に伴う不調(PMS)
- PMSとは
- PMSの原因
- PMSの診断
- PMSの治療
月経に伴う不調(PMS)とオーソモレキュラー栄養療法
オーソモレキュラー栄養療法とPMS

月経のある期間、女性は排卵と子宮内膜の変化を繰り返しています。
この月経周期にともなう変化は主にエストロゲンとプロゲステロンなどの女性ホルモンの働きによって調節されています。月経に伴う不調にはこれらのホルモン分泌に関係するものが多く、月経前の乳房の変化などを感じられることも多くあります。
月経がはじまる7~10日前から始まる、イライラや抑うつ感などの精神症状を伴う各種の不調はPMS(月経前症候群)など診断され、通常では漢方薬やホルモン剤などが処方されます。それらの治療によってつらい症状が改善することもありますが、精神症状にたいしては抗不安剤や抗うつ剤などが用いられることも多くあり、その後の妊娠を考える女性の患者さんにとっては投薬に抵抗感を感じる方も少なくありません。
ホルモン剤の副作用には低いとはいえ乳がんのリスクが上がることや血管の中で血液が固まりやすくなる血栓易形成が知られています。
みぞぐちクリニックでは、全員の方に詳細な血液検査をおこなっているため、ホルモン剤服用中の患者さんの多くに微小な炎症を認めることが多く、血栓易形成の状態になっていることが理解されます。
オーソモレキュラー療法では、PMSや月経痛など月経にともなう諸症状にたいしてホルモン剤を用いないアプローチが行われます。

EPA(エイコサペンタエン酸)
魚油に多く含まれるω3系の脂肪酸の1つで、炎症を抑える作用、血小板が集まり血液が固まるのを防ぐ作用があります。これらの作用はホルモン剤を用いているときには、ホルモン剤の副作用を軽減することになります。さらにPMSや月経痛の症状の背景には、微小な炎症が関係していることが多く、ホルモン剤を用いていない場合においても有効です。
γ-リノレン酸
月見草オイルなどに多く含まれるω6系の脂肪酸の1つで、ヨーロッパでは女性のためのオイルと言われることもあります。EPAとは少し異なる作用によって炎症を沈め月経に伴う各種の症状に効果が期待されます。特に月経痛や月経にともなう関節痛などの痛みを伴い症状には効果が期待される成分になります。
イソフラボン
月経に伴う諸症状には女性ホルモンが多く分泌されすぎることによって起こる症状もあれば、分泌量がたりないことによって起こる諸症状もあります。またこれらの諸症状が月経周期のなかで混在することもあるためホルモン補充療法によって改善するものもあれば増悪してしまうこともあると考えられます。イソフラボンは、その構造が女性ホルモンであるエストロゲンに近いため、エストロゲンが足りないときにはエストロゲンのように作用し、過剰なときにはエストロゲンの作用を減弱するように作用する特徴があります。
ヘム鉄
1回の月経では約30㎎の鉄を失うとされています。実際には月経による出血がある前に子宮内膜が妊娠に備えて厚くなるため身体中の鉄分が子宮内膜に集められます。そのため月経が始まる数日前から身体とすると鉄欠乏が進むことになります。月経にともなう多くの精神症状や月経痛などにも鉄不足は深く関係しているため、鉄欠乏を正しく評価し補正することは基本的で大切なアプローチとなります。鉄の補充では、用いられる鉄の種類によってかえって炎症が増悪してしまうことが多くあるためできるだけ赤身の肉などの食材、ヘム鉄など吸収率の高いサプリメントなどを用いることをお勧めします。
ビタミンB群・ナイアシン
PMSや月経痛などの改善には鉄不足の補正が重要ですが、私たちの身体は鉄を利用するためにビタミンB群やタンパク質が必要です。ビタミンBのなかでもビタミンB6は鉄の利用で必須となるポルフィリン環を作るために必須であるため、ビタミンB6の不足時には鉄を補充しても効果が得られないことがあります。またビタミンB群とナイアシンは多くの神経伝達物質の生合成でも必要でありPMSに付随する多くの精神症状の改善のために補正します。
オーソモレキュラー療法では、これらの栄養素を血液検査や症状などから選択し総合的な改善を目指します。効果については自覚症状とともに血液検査を定期的に行うことによって評価しています。
一般的な治療法

月経に伴う不調(PMS)
月経に伴う不調(PMS) 女性はライフステージの変化とともに、生理(月経)に伴うさまざまな症状が出ます。ここではPMS(月経前症候群)を取り上げます。
PMSとは

PMSとはPremenstrual Syndromeの略で、生理前に起こる様々な不調を指し、日本語では月経前症候群と呼ばれます。
生理の3-10日位前から心や身体の不調が起こり、生理が来ると症状が弱まり、やがて消えていきます。
PMSの症状は人によってさまざまで、同じ人でも月によって症状が違い、その種類は200以上と言われています。
主な症状には以下のようなものがあります。
心の症状
- わけもなくイライラする、怒りっぽくなる
- 些細なことで落ち込む、憂うつな気分、抑うつ状態になる
- 情緒不安定になる、やる気がなくなる、不安を感じやすい
- 集中力が低下する
- 落ち着かない
- 泣きたくなる
身体症状
- 乳房の張り、痛み
- 肌荒れ、にきびができやすくなる
- 食欲が増す、過食、食欲不振
- 疲れ、だるさ、しびれ、ほてり
- めまい、頭痛、頭の重い感じ
- 眠気、中途覚醒、睡眠障害
- 便秘、下痢、腰痛
- 吐き気、気分不良
中には精神症状が強く日常生活が困難になる人もいます。
そのような場合、PMDD(Prementrual Dysphoric Disorder:月経前不快気分障害)が疑われます。
PMDDという名称がついたのは1994年と比較的新しく、2013年に抑うつ症状群の一つと捉えられるようになっています。
日本では生理(月経)のある女性の約70-80%が生理前に何らかの症状があり、PMDDは1.8-5.8%が該当するという統計があります。
PMSとライフステージ
生理が始まったころは不順なことが多く、女性ホルモンの働きが安定してくるのは18歳ごろです。それから閉経を迎える40~50代の間の症状には年代によって異なる傾向があるようです。
20代の女性は下腹部痛や頭痛など身体症状が強く出る傾向にあり、30代になると、精神的に不安定になったり、攻撃的になるなど精神症状が出やすくなります。
30代は仕事や結婚、妊娠、出産、子育てなど多忙でストレスを感じやすい時期です。一般的に出産経験のある女性の方がイライラする、怒りっぽくなるなど精神的な症状が多くみられます。

PMSの原因
PMSは人によって大きく症状が異なりますが、その原因ははっきりとはわかっていません。
排卵のリズムがある女性の場合、排卵から生理までの期間(黄体期)にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が多く分泌されます。この黄体期の後半に卵胞ホルモンと黄体ホルモンが急激に低下することが原因であると考えられています。
また、脳内のホルモンや神経伝達物質、ストレスなども影響を及ぼしていると考えられ、PMSは多くの要因から起こるといわれています。
PMSの診断
PMSは上記に挙げたような症状が生理前に毎月現れ、生理開始後に和らぐことが特徴です。
症状を記録し、生理周期との関連性を確認します。また、症状が似ているうつ病や精神神経疾患でないことを確認します。

PMSの治療
PMSの程度は人それぞれなので、症状に応じた対策をしていく必要があります。
1.生活習慣の改善
- バランスのよい食事:食事の摂り方に問題があると、体重増加やむくみ、乳房痛などが起こる原因となり、PMSの症状を悪化させる可能性があるので注意が必要です。また、アルコール・カフェインはイライラ、緊張感などを高める原因となるため、摂取を控えた方がよいです。
- 適度な運動:体をゆっくりとほぐすようなストレッチ、ヨガ、散歩などもお勧めです。アロマを使ってリラックスを促したり、深呼吸や瞑想することも効果的です。
2.薬物療法
排卵抑制療法(排卵を抑える治療法)
排卵を止めて女性ホルモンの変動をなくすことで症状を軽減する方法です。
低用量経口避妊薬(OC、低用量ピル)や低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP)は少ないホルモン量で排卵を止めます。
症状に対する薬剤
痛みに対しては鎮痛剤、むくみなどの水分貯留症状に対しては利尿剤や抗アルドステロン療法、精神神経症状に対しては精神安定剤、便秘・下痢には整腸剤などを使用します。
漢方薬
「気」「血」「水」のバランスを整えるため、症状に合った漢方薬(生理痛には桂枝茯苓丸、イライラには加味逍遙散料や抑肝散加陳皮半夏、頭重感やめまいには当帰芍薬散料など)を用います。
記事執筆者
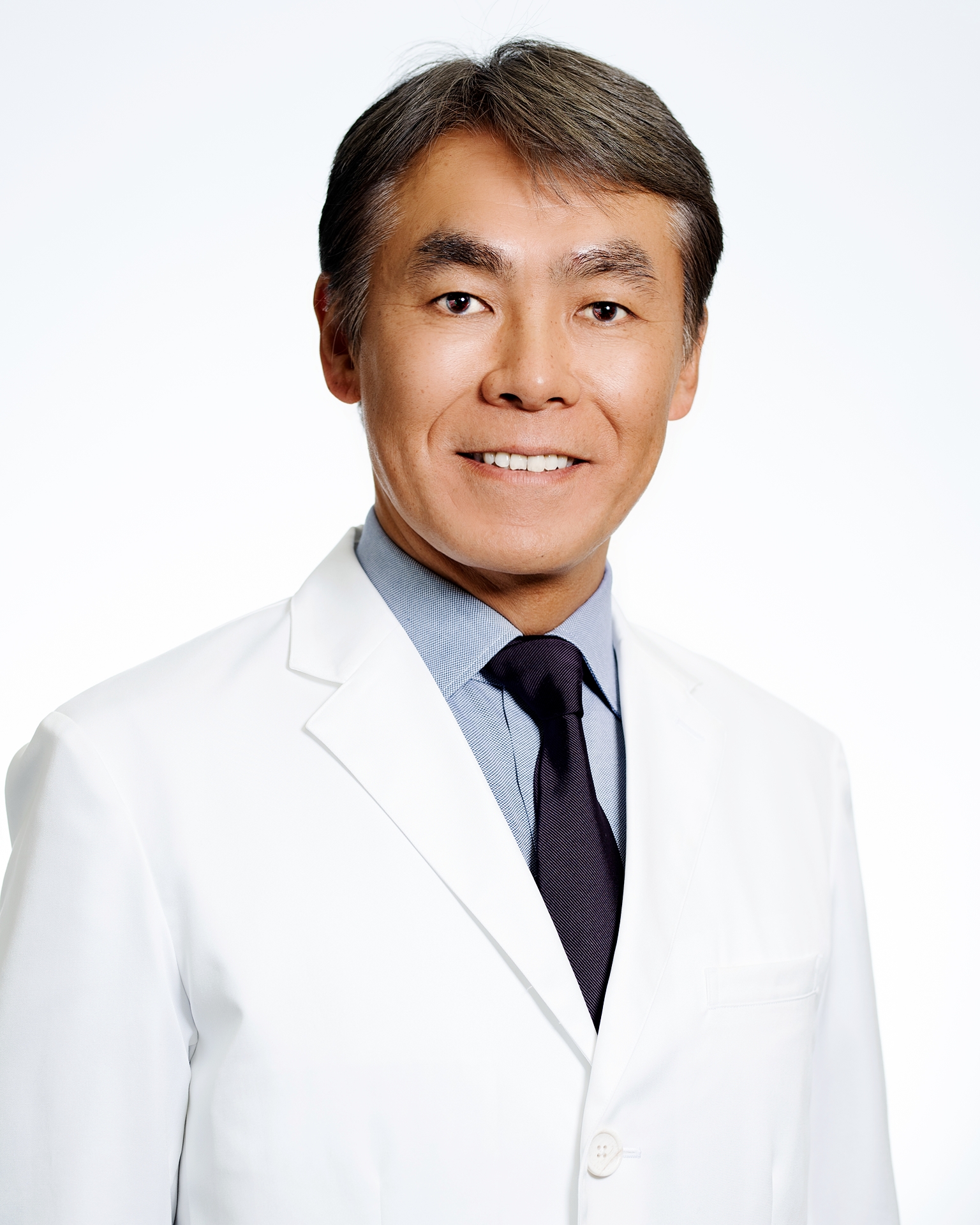
医療法人 回生會 理事長
みぞぐちクリニック 院長
溝口 徹
所属・資格
- 栄養解析医
- 栄養解析レポート監修
- 社)オーソモレキュラー栄養医学研究所 代表理事
- 日本抗加齢医学会 評議員
- 2018年国際オーソモレキュラー医学会 Hall of Fame
- 2020年第2回日本オーソモレキュラー医学会総会 会頭